佐々木 秋子・F.シューベルト : 即興曲 D.899, Op.90 & D.935, Op.142
2010年1月10日発売
HERB-012 3,150円(税込)
録音:2009年2月15日-17日 新潟県魚沼市小出郷文化会館
レコード芸術2010年2月号で準推選盤に選ばれる。
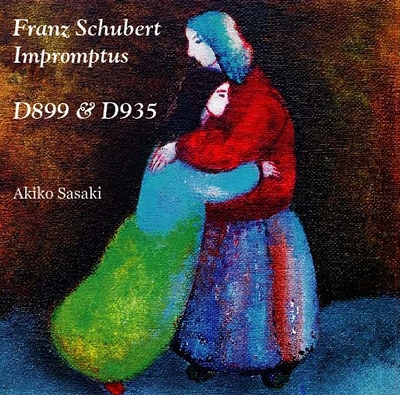 ライナーノートより
ライナーノートより
佐々木秋子の演奏はあくまでも端正である。
モーツァルトやベートーヴェン、シューベルトらの古典的作品には、ピアニストの誰もが演奏したがり、また超人的な技倆が伴わなくとも比較的完成度の高い演奏ができるため、「手垢のついた」といった形容詞が付されがちだ。さまざまな演奏を通して誰もが知っている曲の演奏において、「端正さ」は「凡庸さ」と紙一重であり、そこで個性を表現することは並大抵ではない。だから多くのピアニストは、飽和市場を生き抜くために、個性の演出に勤しんで差異化に励むこととなる。かくして、思い入れたっぷりのフレージングで個性を主張する者、大向こうを唸らせる高い技倆を見せつけようと指の高速回転に賭ける者、楽譜に忠実な演奏に還ると称して硬直したオリジナル楽器の禁欲世界にひたる者、はたまた誰も思いつかないような奇抜な解釈を演じてみせる者....、とCD市場は賑やかしい。しかしこれらさまざまな努力にもかかわらず、いや、そんなことをしているからこそ、クラシック音楽の市場は結局ますます飽きられつつある。
個々のフレーズを思い入れたっぷりに弾いて強調したり、思いつきで人を意外感で楽しませる演奏によって、聴衆を刹那的には面白がらせたり特定のファン集団を惹きつけたりすることもできるだろう。しかし、それらの多くが、曲の本質的構造とは何の関係もないことを、佐々木秋子はおそらく知り尽くしている。だからこそ佐々木は敢えて端正さにこだわり、それによって自らの技倆を磨き上げてきた。そして彼女のそうした地道な努力は、ここ数年のめざましいコンサート活動の中で見事に花開きつつある。独奏と並んで室内楽を主要なフィールドとする佐々木が、ヴァイオリンのヴェルナー・ヒンクやクラリネットのペーター・シュミードルといった著名な演奏者たちから絶大な信頼を得て、その来日のたびに指名されコンサートや録音での共演を行うに至っているのも、こうした佐々木の演奏の高い質に由来するのであろう。
たとえば、それこそ手垢にまみれたモーツァルトの「トルコ行進曲」(ピアノソナタK331第3楽章)を佐々木秋子が弾くとき(ハーブクラシックスHERB-007“SOAR“)、私たちはそこに表現される曲の構成感とみずみずしい響きに新鮮な驚きを感じる。力強く弾き飛ばされることの多いこの「行進曲」を、佐々木はフレーズ毎にていねいに積み上げてゆく。8小節ごとのフレーズの切れ目に入る大小さまざまなルフトパウゼは、もしかすると意識してのものではないのかもしれないが、これは佐々木が、個々のフレーズがどのように立ち上がり、そしてどのように無の世界へと再び還ってゆくのかを、音楽の精神に忠実に表現しようとしたことの副産物なのだろう。こうして一つ一つのフレーズがしなやかに呼吸し始めるとき、その積み重ねの中から曲全体に生命が与えられ、最後の頂点へと向けてエネルギーが次第に高まる見事な構成が浮かび上がってゆくのである。
この曲に限らず、佐々木が弾くピアノには、機械的なビートのリズムとは無縁の、微妙なテンポの揺れが常に伴っている。それは、恣意的な感情表現とは無縁の、音楽そのものの呼吸が表れた自然な揺れであり、これこそが佐々木秋子独自の「端正」な音楽の、一つの重要な骨格をなしている。それは、楽譜をなぞるのではなく、音楽が作り出されてゆくエネルギーの流れを体感して「今・ここ」に音楽が立ち上がってゆく瞬間を可能とする端正さなのである。
この佐々木が今回シューベルトに挑戦した。選ばれたのはよく弾かれる二つの即興曲集であるが、これらはまた、20代後半にしてあまりに早過ぎる晩年を迎えたシューベルトが好んで表現した「光と影」の両面を持つ意味深長な名作でもある。長調の旋律の下に悲しく深淵を覗き込むような眼差しを宿す「光と影」の二重の表現は、もともとハイドン流の屈託ない伸びやかな長調表現から成長したヴィーン古典派の音楽が、たった数十年のうちに辿り着いた一つの終着点とも言うべき独特な表現世界であったと言えるだろう。端正な長調によって表現される悲しみには、直截的な短調表現では及びもつかない、筆舌に尽くしがたい万感の思いが籠められることとなる。これは、例えばやはり同じく夭逝したモーツァルト最期の(まともな演奏であれば)異様に静かなピアノ協奏曲(B-Dur, KV 595)などに典型的に見られるものであり、そしてシューベルト最晩年のピアノソナタはこれを痛々しいほど徹底的に表現し尽くしたものであった。とかく佳作として扱われがちなシューベルトの即興曲集もまた、これら3曲のピアノソナタと同じ精神の下にある。「おもしろうてやがてかなしき」とは芭蕉の句の一節だが、シューベルト晩年の音楽では、「おもしろ」そうに笑いさざめく響きが輝けば輝くほど、そこに同時に「死の風景」が立ち現れて響き合うのである。ちなみに「死の風景」とは、アドルノによる卓越したシューベルト理解(『楽興の時』)のキーワードであった。
とはいえ、ささやかに笑いさざめくシューベルトの音楽は、残念ながらそもそもまともな演奏をしてもらえないことがあまりに多い。とりわけ交響曲の場合、『未完成』より前の曲は「若書き」の作品として軽視され、例えば「小ハ長調」と称される第6番交響曲第1楽章の場合、木管たちがあちこちで笑いさざめくような曲想が、煽り立てるテンポと暴力的な打楽器の濫用とによって台無しにされていない演奏に出会うことなど至難の業だ。音楽の理念や構造への思考を遮断して平気な態度は、近年のオリジナル楽器ブームに乗った多くの未熟でつんのめった演奏によって加速度的に広まってしまったが、そのような演奏を通して、ひどく傷つきやすいシューベルトの音楽が表現する「おもしろさ」と「かなしさ」の共存する深淵な世界を垣間見ることは、ほとんど不可能であるに違いない。ついでに言えば、シューベルトを「素朴」で「非反省的」で「無垢」で「叙情的」な音楽家と位置づけて安心することの多い音楽批評家たちは、これら凡百の演奏と共犯関係にある。
シューベルトの音楽には、時間をたっぷりかけて音楽に心ゆくまで語らせ、細部を無心に慈しむ端正な演奏こそがふさわしい。そしてそのような演奏への期待を、佐々木秋子は裏切らない。静寂の中から佐々木が一つ一つのフレーズを、ゆっくりと大切に愛おしみつつ立ち上げるとき、おもしろうて同時にかなしきシューベルトの、心を張り裂くような音楽の世界が、聴く者の心にしっとりと広がってゆく。既に数多くのCDが存在するシューベルトの即興曲ではあるが、佐々木秋子という演奏者に出会ってくれたことに感謝したい。とりわけ即興曲D.935,Op.142の第2曲や第3曲を、佐々木秋子が明るく健気に響かせるとき、その端正な一音一音はあたかも、この世と別れを告げようとする人が、既に彼岸から遙か現世を振り返って万感を籠めて懐かしんでいるかのようにも響き、きっと聴く者の涙を誘ってやまないことだろう。
相澤 啓一 (ドイツ文学)
 前のページへ
前のページへ